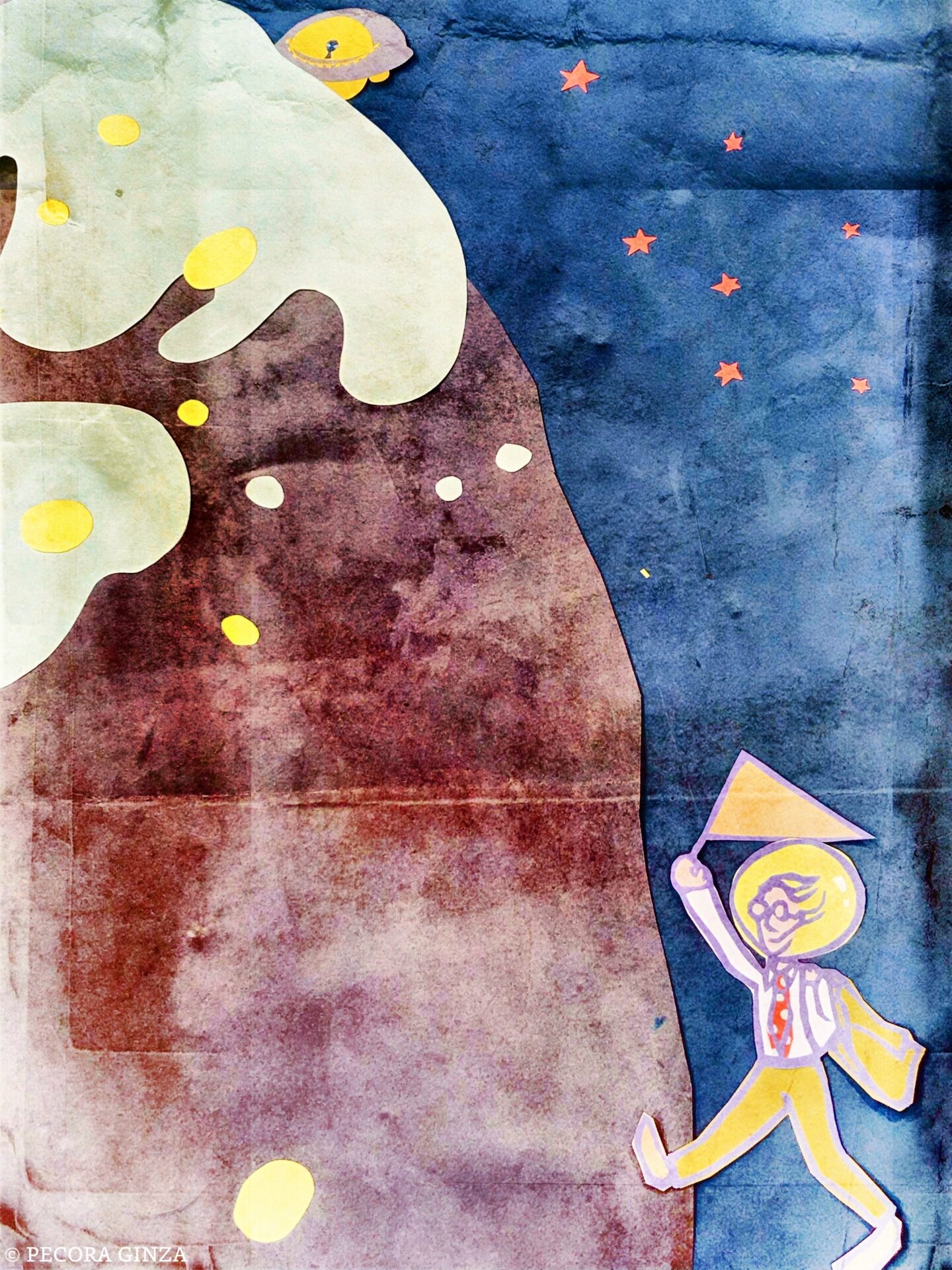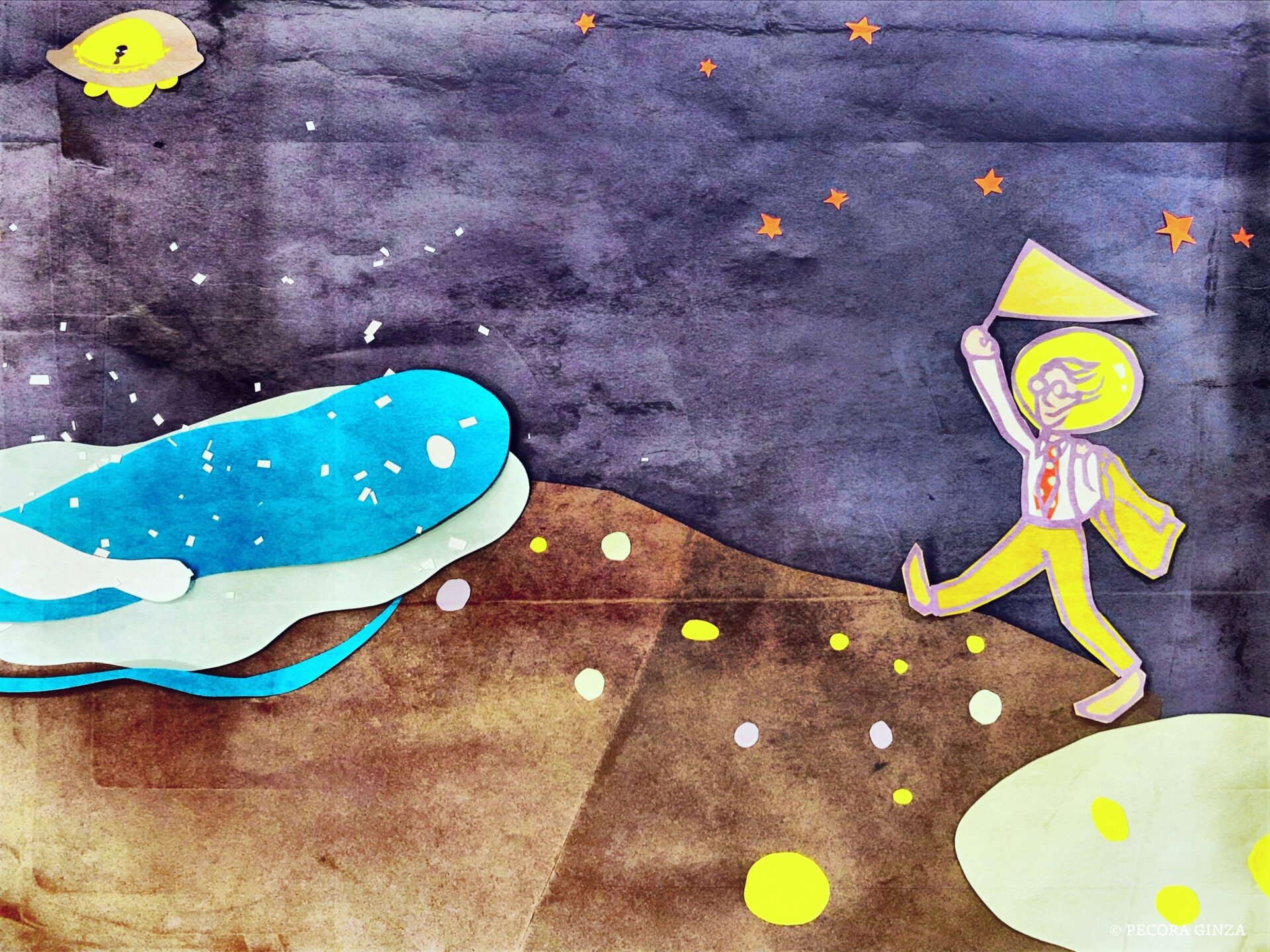こんにちは。黒田です。
ペコラ銀座お洋服研究日記。
<page.6>
ある作家の講演を聞きに行った際に、その作家自身が実践する本の読み方として‘同時に数冊の本を読む’という本の読み方を知った。以来、私もその作家を真似て、本を読む時は側に数冊別の本を置いて読書することを好むようになった。
この研究日記で今主軸となっている「服装と階級」の本を読む側にも、その他複数冊の書物がある。
本を読みながら沸き起こる、「ん?これどうゆう意味?」「あ、ここもっと知りたい。」と言う気持ちと向き合う事を助けてくれる、これら複数の書物。
今日は、この数冊合わせて知る事が出来た、近代初期頃の貴族の‘あの装い’についての話。
・・・
「服装と階級」の本のつづきを読んでいた。
・・・
18世紀末頃にもなると、服地や装いが人の社会的立場と経済力を示すものであると言う認識は欧州社会の人々の中で深く根付いていた。
それまで何世紀にも渡って「服地」には階層身分を明らかにする‘文字で書かれない暗号’が織り込まれており、その服地を用いた装いは社会的立場を示すメッセージを発信するのであった。
貴族たちは階層身分社会を正当化するために‘身分とは、神の定めである’と言う思想を唱え、奢侈禁止法によって自分たちの‘豪華な装い’を独占し続けた。身分の低い者は毛皮や絹などの高級服地を買うことは許されず、数世紀に渡ってそれらの服地はエリートのための服地として‘保護’されていた。
そんな、‘装いと外見が命’であった貴族政治の時代がピークを迎えたのは「リネン」誕生の頃ではないかと、歴史家Daniel Roche氏はいう。
当時、リネンは多用途に用いられ、家庭内のシーツやテーブルクロス、ナプキンなどにも使われた。
そして服地と言う面においては「リネンと言えば – シャツやバンド(ベルトのようなもの)、ラフ(ひだ襟)、それから寝巻きや下着に- 最も適した高級生地」だったそうだ。
「高級生地である」事に加え、リネンにはもうひとつの価値があった。それは「とても丁寧なケアを要する、手間のかかる服地である」と言う事。丁寧な扱いが必至である事は、この服地を用いる者の社会的立場や優位性を示す事と密接な関係があった。
丁寧なケアを必要とするリネンが、富と権力の象徴に関係した例に貴族たちの装いを飾るラフ(ひだ襟)がある。
ラフ(ひだ襟)は一度着用し終わると、その都度一から新しく整形しなければならない装飾品であった。一度着用したラフ(ひだ襟)は洗濯されると一枚のリネン生地に戻り、およそ5時間もの時間をかけて再びラフ(ひだ襟)に作り直されるものであった。
装いに「時間と手間をかける事が出来る」と言う事も、贅沢さや富そして品格の証となるのであった。
・・・
なるほど。「手間がかかる」「時間がかかる」事が贅沢と富の証となる事に、私は大いに納得した。
それにしても、貴族たちはおもしろい。
装飾的で豪華な服地で仕立てた服を纏い、金銀財宝で身を着飾ったその先は、‘ものすごく手間のかかる事’を意義とした更なる装飾品を装いに加えて自らの富を更に主張し、競い合っていたのか。
ペコラ銀座店主にこの話をしたら「あー昔のリネンってものすごい良いリネンだったんだろうな。あ〜〜〜〜見たいな〜、触りたいな〜。リネンって、本当、良いのがどんどん無くなってきてるんだよ。。。そうそう。実は今日、ちょうど、物凄く良いリネンを裁断したんだ。ペコラさんが良く僕に‘昔のアイリッシュリネンは最高だった’って言ってたんだけど、今日裁断したリネンは、僕がずっと見たいな〜と思っててやっと見つけた最高のリネン生地だったんだ。」と、生地マニアならではの反応を見せていた。
それから最後に一言「そういや、あの‘えり巻き’ってどうやって作ってたのかな〜?」と、店主の疑問が浮上した。
。。。
あの‘えり巻き’が、ラフ(ひだ襟)と呼ばれる富の象徴である事は分かった。でもそれをどうやって作ってたか?
わたしは側にあった「エリートの服装」の本を手にとり、読みはじめた。
・・・
明白な実用性を持たないラフ(ひだ襟)からは、現代と近代初期の装いにおける‘感性の違い’が垣間見えるものである。
このチューダー王朝文化のアイコン的な装いは、絵画に描かれているが故につい想像してしまう‘永久性をもつ’イメージとは裏腹に、実は‘1日限り’という儚い宿命を持つ衣服であった。
ラフは、その形状を保つようには仕立てられておらず、それは洗濯する度に「作り直される」前提のものだった。
典型的なラフは、10メートルほどの細長いリネンから出来ている。そのリネンは数百ものプリーツに折られ、手縫いによっておよそ50cmの長さのラフ(首襟)が作られる。
一度着用された後のラフは、洗濯され、糊付けされ、プリーツに折られ、手で縫われたのちに、ポーキングスティックと呼ばれるアイロンを使って形がセットされ、再びラフとして生まれ変わる。
このラフが生まれ変わる工程にはかなりの時間と労力、そして高い技術が必要とされ、「‘1日限り’のラフを繰り返し毎日誂える」ためにはかなりの富と権力を要するのであった。
さらに、ラフは出来上がった後、ピン打ちによって首回りに固定して着用し、この着脱作業にも複数人の手助けが必要となった。
これらのことから、やはりラフは、身の回りの世話をしてくれる使用人に囲まれる貴族ならではの装飾品であった事がよく分かる。
・・・
なんとまあ。知らなかった。
あの‘えり巻き’に、こんなにも時間と技術が注がれていたなんて。しかも、1度きりという儚い命。
時間を要し、技術を要し、装着には人の助けを要し、なんと言ってもこれを「毎日毎日‘誂え直す’ことが出来る」という事が、この‘えり巻き’に込められた富の象徴だったのだ。
それは、手間隙という名の富だったのだ。
・・・
‘えり巻き’の事を知り、私が感じたことは「いかに時間と技術と、人の手をかけたか」ということに対して大いなる価値を感じる事の出来る人の感性が、ずっと昔から確かに存在したと言うこと。
そして「人の手作業、人の時間、人の技術」と言うものの価値は、金銀財宝にも勝る宝物であると言うこと。
それから思い出すのは、ペコラ銀座店主、佐藤英明の洋服づくりにおける信念である。
「どんな手間隙も惜しまず洋服づくりをする事。ひとつの手間を変えただけで、そのものの味わいが変わる。どんなに面倒でも、手間隙を惜しんではいけない」そして、「どれくらい手間隙をかけたかと言う事は、絶対に裏切らない」と彼は言う。
形を持たない「手間隙」と言うものが形にするのは、無限大の価値と言う宝物である。
その事を、‘えり巻き’の事を知る中で、あらためて感じるのだった。
memo…手間隙は惜しむべからず。何よりも大切なこと。